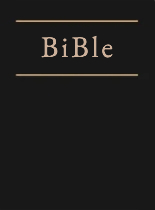-
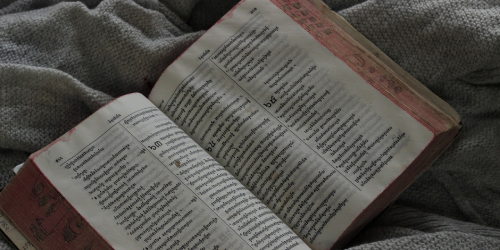
- 「まことのぶどうの木に繋がって生きる」ヨハネ15:1-10 槙和彦
詩編80:9-20、ヨハネによる福音書15:1-10私たちは、2018年の10月に、この教会の会堂で、「特別伝道集会」としてラテン音楽の演奏会を行いました。演奏を披露した「私たち」というのは、私と妻とその他3人の仲間たち(そのうち一人は2019年2月に亡くなった、ラテン音楽の大師匠である納見義徳さん)でしたが、そこではラテン音楽の演奏に加えて、私から少し長い話をする機会も与えられました。「三つの出会い」、すなわち私がラテン音楽と出会い、妻と出会い、さらに教会と出会った経緯について、一般のオーディエンスの皆さま向けにお話をさせていただきました。その時の原稿が教会のホームページにもそのまま載っていますので、ご興味のある方は、そちらもぜひお時間のあるときにお読みいただければと思います。今日は、その
-
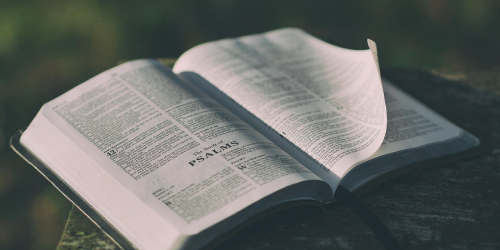
- 「それでも人は立ち上がる」ミカ書7:1〜7 中村吉基
ミカ書7:1-7;マタイによる福音書25:31-46人間誰しも何をやってもうまくいかない、八方ふさがりの時があります。そういう時にはがむしゃらに行動に出ないことをおすすめします。神から自分を見つめ直す時が与えられたのだとして、自分磨きの時として過ごすことです。のんびりしていればいいのです。私たちの人生には、人に裏切られたり、病気にかかったり、突然の災害に襲われたりする時があります。そういうときに皆さんが陥ってしまうのは、もはや右にも左にも、前にも後ろにも「突破口」「逃げ道」がないように思ってしまうことです。「どうせ私の苦しみなど、理解してくれる人はいない」と、自分自身で引きこもってしまう人もいます。しかしそれでは、ますます皆さんは、八方ふさがり、そして孤独な状況に追い込まれてしまうのではない
-
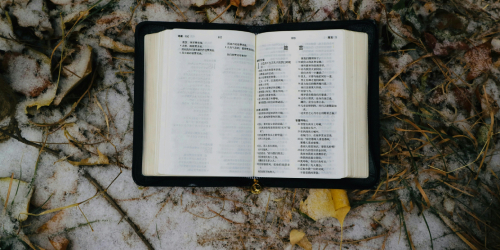
- 「本当にこの人は神の子だった」マタイ27:32-56 中村吉基
哀歌5:15-22;マタイによる福音書27:32-56日から受難週(Passion Week, Holy Week, Semana Santa)に入ります。イエス・キリストの十字架への道行きの一週間です。今朝はマタイによる福音書から受難の物語の一部を読みました。この受難物語というのは4つの福音書すべてに書かれてあります。それぞれに視点が違い、個性があって記し方は違うのですけれども、福音書を書いた弟子たちというのは、まずこの主イエスの受難と死と復活というところから書き始めたと考えられます。そしてそのあとで主イエスの誕生物語や生涯の記録が加わっていった。まさにこの受難週に起こったことは強烈な印象として弟子たちの心に残っていたと思うのです。そしてこの残忍で、空虚な出来事――しかし、それは主の復活の
-
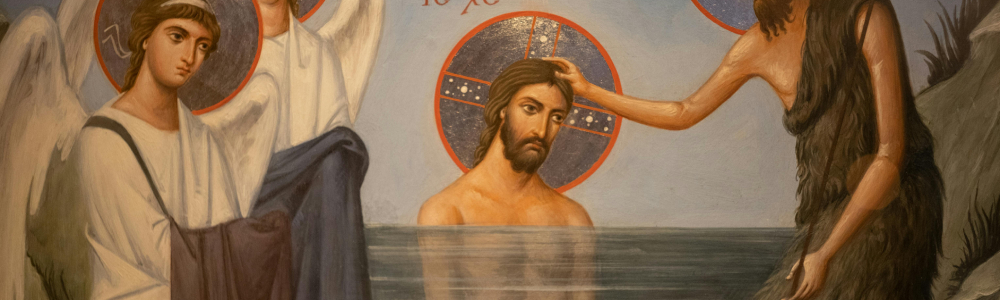
- 「常に喜びなさい」フィリピ4:4-9 中村吉基
士師記13:2-14;フィリピの信徒への手紙4:4-9アドヴェント・クランツに3本目のろうそくの灯がともりました。今日のろうそくの色は少し違っています。これまで紫のろうそくを2本点してきましたが、今日待降節第3主日のろうそくはばら色のろうそくです。実は、待降節の4回の主日(日曜日)にはそれぞれ別名を持っています。先々週の第1主日は「希望」、先週第2主日は「平和」、そして今日第3主日は「喜び」、そして次週第4主日は「愛」というようになっています。今日は喜びの主日です。別名「ばらの主日」と言います。「人生ばら色」って言いますよね。万国共通「薔薇」は素敵なものの象徴です。クリスマスがもうそこまで近づいてきたことを実感する日曜日が今日なのです。待降節に入ったときに私は「主の到来を待ち望みながら、自分
-
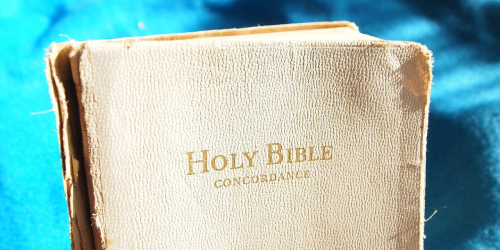
- 「神の国はあなたたちのところに」マタイ12:22-32 中村吉基
イザヤ書35:1-10;マタイによる福音書12:22-32聖書の時代には、病気や災いは悪霊の仕業と考えられていました。今日の箇所には悪霊によって目の見えない、口の利けなくなっていた人が主イエスによって癒されるというエピソードが記されています。この光景を一部始終見守っていた群衆たちは「この人はダビデの子ではないだろうか」(23節)と言った、と福音書は伝えています。「ダビデの子」というのは今まで民衆が待ちわびた救い主という意味です。ヘブライ語聖書ではメシアはダビデの子孫から出るとされていたからです(サム下7:12-14,イザ9:5−6,11:1-5など)。岩波書店訳の聖書では群衆が「度を失うほど驚嘆し」(佐藤研訳)とあります。まさに興奮状態にあってこう言ったわけです。ですから主イエスの行く先々に
-

- 「安心しなさい 恐れるな」マタイ6:22-36 中村吉基
イザヤ書30:8-17;マタイによる福音書14:22-36週日の夜、オリーブ会でキリスト教や聖書の手ほどきをしています。本当に時を忘れるほどの楽しい学びをしています。しかし、今週の週報をごらんになると、木曜日のオリーブ会のところにいささか物騒なテーマが掲げられています。「神なんて本当にいるのか?」聖書の記述も、教会の信仰も神は「存在されるもの」として告げられています。しかしそれよりももっと前の段階として「神なんて本当にいるのか?」というテーマで学びをするのは、現代人に向けて挑戦的なことと言えます。「信仰というものは、99パーセントの疑いと、1パーセントの希望だ」と言ったのは20世紀フランスのカトリック作家ジョルジュ・ベルナノス(1888−1948)です。長く教会生活を送ってきた人、篤い信仰の
-
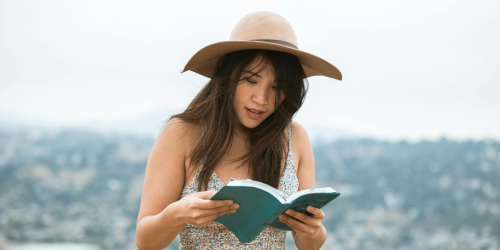
- 「かけがえのない存在」ルカ15:1-10 中村吉基
出エジプト記32:7-11,13-14;ルカによる福音書15:1-10今日は最初に考えてみてほしいことがあります。皆さんが電車の運転士だとします。今皆さんが運転している電車は100キロ近いスピードで走っています。ところが前のほうを見ると、5人の作業員が工具を手にして、線路上に立っていました。皆さんは電車を止めようとしますが、もうブレーキが利きません。このまま行くと5人を轢いてしまうことになります。その時、ふと右のほうを見ると退避線がありました。ここにも作業員がいましたが、1人だけでした。皆さんがこの状態に立たせられたらどうするでしょうか。まっすぐ進んで、5人を轢くでしょうか。それとも退避線に入って1人を轢くでしょうか。5人轢くよりも1人のほうが、被害が少ないので、退避線に入ることは正しいこと
-

- 「それでも朝は来る」マタイ28:1-10 中村吉基
創世記1:1-5,26-31;マタイによる福音書28:1-10皆さん、イースターおめでとうございます。ずっと以前のことになりますが、私宛てに一通のメールをいただきました。お名前を見ると私の存じ上げない方でした。その方のメールにはあるカトリックの司祭の死が告げられていました。以前私がその神父のことを説教の中で紹介させていただいたことがありました。メールをくださった方はおそらく神父のことをネットで検索していくうちにその文章を見つけられたのでしょう。メールの送り主は一生懸命にネット上で神父の足跡(そくせき)を辿られたのでした。その当時の文章を紹介させていただきます。私がとても大切にしている一本のビデオがあります。しかし、私はそのビデオの存在をしばらく忘れておりました。先日久しぶりにそのビデオが出て
-

- 「あなたがたのところに来る」ヨハネ14:15-21 中村吉基
エゼキエル書11:19-20;ヨハネによる福音書14:15-21今日の箇所は、最後の晩餐の席上で弟子たちに向けてなされた主イエスの「告別説教」と呼ばれるところです。この箇所の中心にあるのは「わたしは、あなたがたをみなしごにはしておかない」(18節)という主イエスの力強い約束です。この言葉を中心にして、16-17節に「聖霊」の約束があり、19-20節には「イエスが共にいる」という約束があります。「あなたがたは、わたしを愛しているならば、わたしの掟を守る」と今日の箇所は始まります。主イエスの掟とはいったい何でしょうか。それは主イエスの弟子たちがお互いに愛し合うことでした。主イエスの思いは神の思いでもあります。主イエスが神に頼むことによってそれは聞き入れられるというのです。復活されたイエスはまもな
-
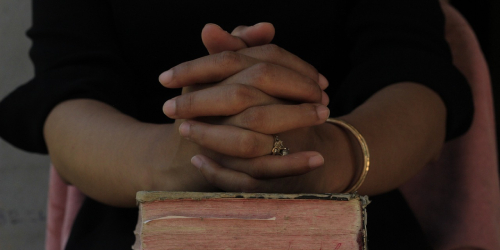
- 「平和をもたらす神の国 」マタイ6:10 徳田 信
詩編103:17-22;マタイによる福音書6:10御国が来ますように。御心が行われますように、天におけるように地の上にも。もう10年ほど前になるかと思いますが、TIMEという国際的なニュース雑誌が、ショッキングな記事を載せました。その号の表紙に掲げられたのは「天国なんて存在しない」という言葉。その記事を書いたのは、イギリス国教会で主教を務めたことがある、NTライトという聖書学者です。ライトは一体どんなニュアンスで、「天国なんて存在しない」という書き方をしたのでしょうか。私たちはよく、地上の生涯を終えて神の御許、天国に行く、という言い方をします。天国に行く、というとき、それは上の方に昇っていくイメージを思い浮かべる方が多いと思います。しかし今回の聖書箇所はいかがでしょうか。イエス・キリストは「
-
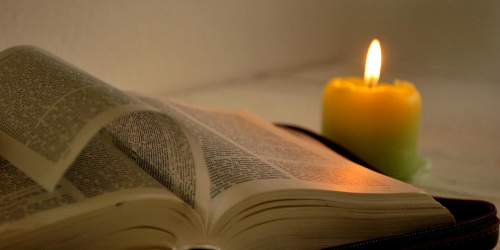
- 「教会に鍵をかけてしまわないために」マタイ16:13-20 中村吉基
ヨブ記1:1-12;マタイによる福音書16:13-20キリスト教のことを「告白する宗教」だと言った人がいましたが、確かに私たちは教会で語られていることを受身のまま聞き流していればいいわけではないし、何かお題目や呪文のようなものを繰り返しあげていればいいわけでもありません。私たちは一人の人間として神の前に、あるいは人々の前に告白をする。礼拝のなかで、いくつもの告白があります。考えてみればお祈りや賛美歌を歌うことも信仰告白です。いちいちそんな告白をしないでもっと気楽な信仰があるかもしれません。しかし、主イエスはただ黙ってご自分に服従させるのではなくて、私たちに「応答」をすることを求めています。たとえばこの礼拝の中でも聖書の言葉に聴き、それを解き明かす説教を聞きます。説教のあとで、皆で祈りを合わせ
-
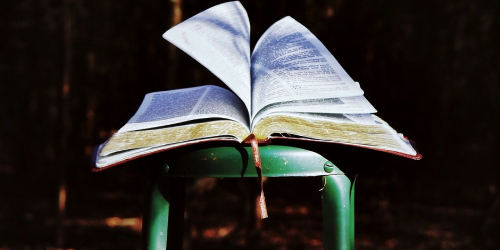
- 「謙遜に生きる道」ルカ3:15–17 2021/01/09 中村吉基
イザヤ43:1–7;ルカによる福音書3:15–17この世界に救い主として来られたイエス・キリストはおおよそ30歳ごろに宣教活動に入られました。ここからの主イエスの歩みは「公生活」「公生涯」と呼ばれます。まず主イエスがなさったのは当時、ヨルダン川の辺りで洗礼運動を繰り広げていたヨハネから洗礼を受けることでした。その後、主イエスはただちに神の国を宣べ伝えて、苦しむ人、悩む人、病める人などに癒しとそこからの解放を告げ始めました。公現日のあとの主日には必ずこのイエスの洗礼の記事が読まれます。主イエスが受けた洗礼の出来事を祝うとともに、私たちが受けた洗礼の意義を考え、またこれから洗礼を受けようとする人には、洗礼の意義に加えて、クリスチャンとして生きることはどういう道なのか、ということを併せて考えてみま
-
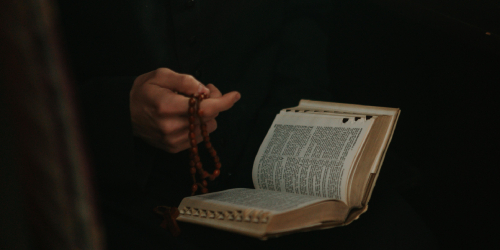
- 「その水をください」ヨハネ4:1-15 中村吉基
ミカ書4:1-7;ヨハネによる福音書4:1-15神は、私たちが思いがけないようなことをなさるお方です。神は私たちの人生に思いもよらないことをお与えになります。そして神は私たちの人生をとても豊かにしたいと願っておられます。今日の聖書の箇所は、主イエスがユダヤを去り、故郷のガリラヤに向かわれたときにサマリアを通られたという出来事から始まっていきます。サマリアと言えばユダヤとは敵対関係にあった人々の住む場所です。紀元前700年代にアッシリアの属州となったときに外国から異民族が連れて来られました。そのときに当然その異民族の宗教ももたらされ、「偶像」に仕えた者たちだとユダヤの人たちからは忌み嫌われていたのです。サマリアを通ればおおよそ3日でガリラヤに行くことができましたが、サマリアを避けて行けば倍の日
-
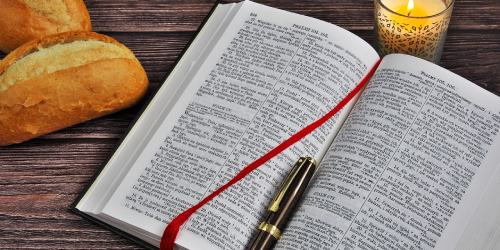
- 「希望」 ルカ14:15-24 広石望
イザヤ書25:1-10; ルカによる福音書14:15-24I 先週の聖霊降臨祭に続き、三位一体主日を本日祝う私たちは、すでにもう100日ほどの間、ロシアによるウクライナ侵攻という巨大で陰鬱な影の中にいます。 一方的な軍事侵攻を受けた国にとって、自国の領土内で侵略者に軍事的に対抗することは、国際法上も認められているのでしょう。サッカーのワールドカップ予選に敗れたウクライナ・チームの一人の選手が試合後のインタヴューで、「誰もが自分の国で平和に、また自由に暮す権利をもっている。世界の皆さん、私たちを助けてください」と涙ながらに訴えていました。 自国の独立と主権を維持するために、諸外国から武器供与という軍事支援を受けることも、侵略した当のロシアを除けば、国際的にほぼ容認されているようです。 しかしな
-
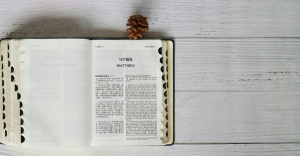
- 「心が折れる?」ルカ18:1−8 中村吉基
創世記32:23−33;ルカによる福音書18:1−8先週は神学生が私たちの礼拝にきてメッセージを取り次いでくれましたが、私が神学校を卒業して、伝道師としての歩みを始めた時、准允(じゅんいん=説教することを許可される…という意味です)式というのがありまして、司式者はテサロニケの信徒への手紙一5章にある有名なみ言葉「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそ、キリスト・イエスにおいて、神があなたがたに望んでおられることです」を引用して勧めの言葉をくださいました。私はこの奨励の内容を「よく」憶えています。司式者は「『いつも喜んでいなさい。・・・・・・どんなことにも感謝しなさい』と言われてはたと困ってしまう。私には『いつも喜ぶ』なんてできないからだ。『どんなことにも
-

- 「いったい、これは……」使徒2:1-11 中村吉基
エゼキエル書37:1-14;使徒言行録2:1-11皆さん、ペンテコステおめでとうございます。一昨日の朝、教会員のお二人に伴っていただいて、H教会を訪問してきました。2月に私が説教奉仕に伺った教会です。教会の方々がチームを作って、素晴らしいガーデンを作っておられるので、それを見学させていただいたのです。何十種類の植物を育てておられます。いつの季節でも花が咲いているものに植え替えておられます。なんと年に2回土づくりからなさっているそうです。H教会は駅と山手通りを挟んで、活気のある商店街の中ほどにある教会です。教会の前はたくさんの人が通ります。美しい教会のガーデンに惹かれて求道をはじめて、洗礼を受けた方が何人もいらっしゃったとお聞きしました。教会の外の掲示板も一つだけではありません。通行される方が
-

- 「イエスに従う旅」ルカ19:28-40 中村吉基
詩編118:19–29;ルカによる福音書19:28-40今日私たちはイエス・キリストの最後の一週間の歩みをたどる受難週を迎えました。そして今日の日曜日はとりわけ主イエスのエルサレム入城を記念する〈棕梠の主日〉と呼ばれる日です。イエスはこのように話してから、先に立って進み、エルサレムに上って行かれた(28)。エリコの町から主イエス一行がエルサレムに「上って」来たと言います。首都エルサレムに上ってきたということですが、エルサレムは標高800メートル小さな山の上に造られた街ですから「上って」来たというのは文字通りのことでした。反対にエリコは世界最古の町であり、海抜はマイナス250メートルですから主イエスたちは1日の間に1000メートルほどの道のりを「上って」きたのです!そしてようやくエルサレムの街
-
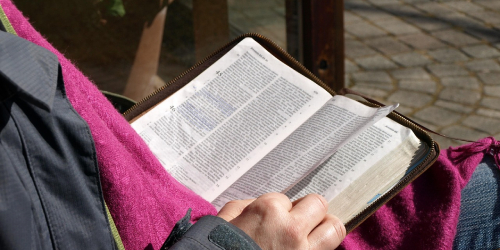
- 「裁きとゆるしと」ヨハネ8:1-11 中村吉基
出エジプト記20:1-17;ヨハネによる福音書8:1-11今日の箇所では、姦通をしていた女性が現行犯で捕らえられ、主イエスの前に引き出されてきます。古代のイスラエルにおいて配偶者以外の者や、または婚約者と性的関係を結ぶことは律法で厳しく禁じられてきました(独身者と関係を結ぶことはキリスト教の時代になってから禁じられました)。ユダヤ人たちの法(ミシュナー)によれば、姦通をした者は絞殺刑に処せられました。石打ちの刑(死刑)は、婚約していながら罪を犯した者への刑でした。ですからこの女性は結婚する前だったと思われます。もちろん男性のみならず女性も同罪となったのですが、なぜかこの場面には相手の男性は出てきていません。どこへ行ってしまったのか、見逃されたのか、どこかへ隠れてしまったのか、真相はわかりませ
-
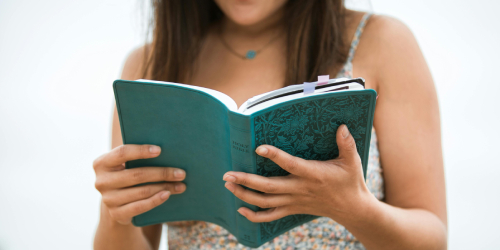
- 「熱心と熱狂の違い」ヨハネ12:12-19 中村吉基
創世記22:1−18;ヨハネによる福音書12:12-19街を歩いていて、電車の中でも、カフェの中でもあらゆるところで、十字架のネックレスやピアスをした人を見なけないことがないほどに、私たちにとってそれは「ふつうの」光景となっています。しかしどうでしょう。死刑のために使われる首に巻くワイヤーやギロチンだったら身につけてみたいものでしょうか。十字架もまた死刑の道具です。韓国で出版された『168の十字架』という書物は日本でも翻訳されましたが、世界中の教会やキリスト教団体などで用いられている十字架が168も紹介されているたいへんユニークな本です。そこにもいろいろな十字架が出てきますが、2000年前のイスラエルで極刑の道具、死刑執行に使われた十字架の恐ろしさはあまり伝わってきません。ローマ帝国では31
-
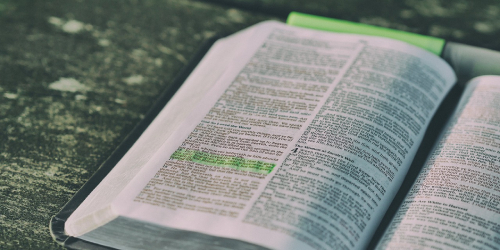
- 「マイム・マイム」ヨハネ7:37-39 中村吉基
ヨハネによる福音書7:37-39神の救いの象徴としての「水」私たちの国日本は「水が豊かな国」などとよく言われますが、聖書の舞台ではそうではありませんでした。雨期になってほんのわずかな雨が降るだけで、乾期には大地が乾ききっているようなところですから、今日のイエスさまのみ言葉にあるように「生きた水が川となって流れ出る」ことなど考えられもしなかったでしょう。私がイスラエルに行きました時には、脱水しないようにミネラルウォーターを手放しませんでした。まだ日本でも熱中症への警告があまりされていない時代でしたから水を手放さないようにと言われるのは、ほとんど経験がありませんでした。そこで見たヨルダン川は濁っていて、清流ではありませんでした。イスラエルというのはたいへん水が貴重な地なのです。皆さんは「マイムマ

- The Cross Pendant
He is a cross pendant.
He is engraved with a unique Number.
He will mail it out from Jerusalem.
He will be sent to your Side.
Emmanuel
Bible Verses About Welcoming ImmigrantsEmbracing the StrangerAs we journey through life, we often encounter individuals who are not of our nationality......